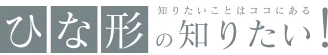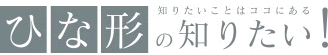
手順・使い方の説明文
「お過ごし」とはたいてい、ビジネスシーンにおいてのメールや文書、目上の方への手紙など改まった文章を書くときに使用されることの多い慣用表現です。改まったビジネス文書や手紙などで、書き出しの時候の挨拶の後に「いかが「お過ごし」でしょうか。」等の一文を続けて、相手の方へ安否の問いかけることが多いですが、文書の最後に結びの挨拶としてお相手を気遣う気持ちを表現する意味でも使います。
手順1
- 「お過ごし」は、「「お過ごし」でしょうか」という疑問形で「どういう状況ですか」「どのようにしていますか」という相手の様子や状態など安否を伺う意味を持っています。また、「「お過ごし」ください」という表現で「今後も良い状況でいて下さい」という相手を気遣う意味にもなります。「お過ごし」には安否を気遣うと共に相手の方を敬う気持ちが込められています。
手順2
- 「若葉が薫る頃となりましたが、いかが「お過ごし」ですか。」
「久しくご無沙汰いたしましたが、お変わりなく「お過ごし」でいらっしゃいますか。」
「初春の候、皆様にはご機嫌よく「お過ごし」のこととお喜び申し上げます。」
「残暑もやわらぎ、朝夕は涼しくなり、過ごしやすい季節となりましたが、お変わりございませんか。」
「まだまだ暑さが厳しい毎日が続きますが、体調に崩さないように「お過ごし」ください。」
「どうか皆様お元気で「お過ごし」下さいますよう、お祈り申し上げます。」
等、時候の挨拶のあとに疑問形の形で続けて、相手の方の様子をうかがったり、後の状態を気遣ったりして文章の締めくくりに用いたりします。
手順3
- 「お過ごし」には慣用的な表現ではありますが、相手の方の安否を尋ねる意味の言葉です。相手の方が、あきらかに心身の体調を崩していたり、良くない状況に陥っているとわかっている場合にもかかわらず安否の状況を尋ねる事は失礼に当たります。使わないように気を付けます。
手順4
- 「いかが「お過ごし」でしょうか」。この一文には、お相手の安否を尋ね、気遣う尊敬の気持ちが込められています。ビジネスシーンでの改まった文書やメール、尊敬する方への手紙などに用いることで、形式的な文章が心の通った気持ちの伝わるものとなり、仕事を、人とのお付き合いを円滑にします。「お過ごし」を用いる事で、相手の方への細やかな心配りを心がけましょう。
Copyright (c) 2025 ひな形の知りたい! ALL RIGHTS RESERVED.