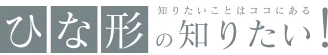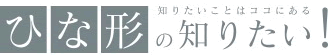
手順・使い方の説明文
相手の方の心中や、立場、境遇などを心配したり、思い遣ったりと、先方の心情に寄り添う時に使う事の多い文章です。心労に「ご」がついた「ご心労」という敬語なので、特に目上の人や上司などに会話や文章には心を込めて使います。また、ビジネス文書に限らず、不慮の災難や病気等お相手の状況を心から心配して、失礼のないように本人やそのご家族に使用される場合もあります。
手順1
- 「ご心労」とは苦労に「心配」「精神の疲れ」「悩み」といった、身体だけでなく精神的にも疲労している状態を意味する敬語です。よく「気疲れ」という言葉を聞きますが、より深刻な症状で、固い言い回しでもあります。これに先方の状況を推測しますという意味の「お察し申し上げます」という言葉が後に続き、「ご心労のほどお察し申し上げます」の一文で、心配な状況を推し測って失礼のないようにお心遣いを示します。
手順2
- 「ご心労のほどいかばかりかと心中お察し申し上げます。」
「ご主人様の突然のご病気のことをお聞きし、奥様の「ご心労のほどお察し申し上げます」。」
「ご家族様の「ご心労のほどお察し申し上げます」。」
「慣れない土地でのお仕事、並々ならぬ御苦労の連続と「ご心労のほどお察し申し上げます」。」
等があります。本来「心労」には、相手を敬う意味が含まれています。そのため、相手の方の「ご心労」すなわち苦悩や心配を推察して表現する言葉として「ご心労のほどお察しもうしあげます。」という文章を用いて先方に敬意を表しつつ、お気遣いの気持ちをお伝えします。
手順3
- 「ご心労のほどお察し申し上げます」の一文は一見相手の事を思い遣っている表現ではありますが、お相手の方は自分が思う以上に深刻な精神状態かもしれないという状況を十分に考慮すべきです。特に自分より立場が上の人には注意が必要です。「私の気持ちが分かるものか」と相手を怒らせてしまう事にもなりかねません。また、直接相手の状況を知ったうえでお伝えし、又聞きなど不確かな情報を元にお伝えする事は厳に慎みましょう。
手順4
- 心身ともに疲弊している方にお気遣いの気持ちを伝えるのは難しい事です。けれども、お相手の心労を知ってしまったら、大人の対応として、お相手の事を心にかけている、思い遣っているということを伝えて、出来る限り相手の心情に寄り添う努力が何より大切です。 そのため、きちんと状況を判断して手紙にしても会話にしても、お相手の正確や周囲の環境なども考慮したうえで、慎重に言葉を言葉を選び、伝える事が最も重要です。
Copyright (c) 2025 ひな形の知りたい! ALL RIGHTS RESERVED.